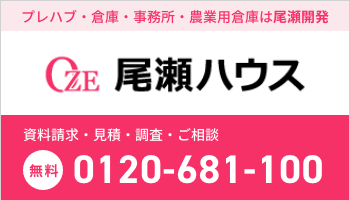自動車整備工場を経営するにあたり、従業員がどのような免許を持っているか、また、その免許でどのような車両を運転できるのかを把握することは、コンプライアンス上極めて重要です。特に、整備工場ではトラックなどの大型車両の取扱いや回送が頻繁にあるほか積載車を運行する場合もあります。そのため、免許制度の理解不足は重大な法令違反や事故を引き起こす可能性があります。
今回は、現在の運転免許制度を整理し、中型・準中型免許を中心に、特にトラック運転における注意点を詳しく解説します。
現行の運転免許制度の基本
日本では2007年(平成19年)に免許制度が大幅に変更され、「中型免許」が新設されました。その後、2017年(平成29年)には「準中型免許」が追加され、免許区分がさらに細分化されています。
現在の区分は以下の通りです。
| 免許区分 | 車両総重量 | 最大積載量 |
| 大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 |
| 中型免許 | 7.5トン以上11トン未満 | 4.5トン以上6.5トン |
| 準中型免許 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 2トン以上4.5トン |
| 普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 |
中型・準中型免許で運転できるトラック
整備工場経営者として特に注意が必要なのが、「中型」と「準中型」免許の範囲です。
中型免許
中型免許は、車両総重量7.5トン以上11トン未満の車両が対象で、主に4トントラックなどを指します。運送業界や建設業界で一般的に使用されるトラックの多くがこのカテゴリに該当します。これらのトラックは車体が比較的大きいため、適切な免許に加え、運転技術が不可欠です。
準中型免許
準中型免許は2017年に新設され、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックが対象です。一般的に2トントラックや小型の宅配トラックなどが含まれます。近年では配送業務の拡大により、このカテゴリのトラックの運用が増えているため、整備工場においても準中型免許の重要性が増しています。
1~2台積みの積載車の多くが車両総重量5~8トンになるように設計されているため、普通に運転できると思っていた積載車でも、普通免許しか持っていない若手では運転できない場合があります。
一方で、いすゞ自動車の「ELF mio」など、車両総重量を3.5トン未満に抑えて普通免許でも運転できるようにしたトラックも発売されています。
出典:ISUZU:エルフミオ(普通免許対応小型トラック)
https://www.isuzu.co.jp/product/elfmio
経営者世代が注意すべき「普通免許」の変化
特に注意すべきは、経営者自身が持つ普通免許の取得時期です。
2007年以前(平成19年6月1日以前)に取得した普通免許は、「8トン限定中型免許」とみなされ、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のトラックを運転可能でした。つまり、多くの経営者世代が取得した普通免許は、現在の中型免許に近い範囲をカバーしていました。
しかし、2007年以降に取得した普通免許では、運転可能な車両の範囲が大幅に縮小されました。さらに、2017年以降は準中型免許が新設され、普通免許で運転できる車両はさらに小型化されています。
若手従業員の免許範囲の実態
現在、普通免許を新規取得した若い世代は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満という非常に限定された範囲しか運転できません。これは、従来の感覚で「普通免許であれば問題ない」と考えている経営者にとって大きな落とし穴となっています。
若手従業員が多い整備工場では、免許区分の変更を知らないまま、誤って中型や準中型のトラックを運転させてしまうリスクがあります。この場合、道路交通法違反となり、会社側も安全管理義務違反として責任を問われることになります。
経営者が取るべき対策
経営者は以下の対策を講じる必要があります。
従業員の免許取得状況を把握する
従業員が保有する免許の種類と取得時期を確実に把握し、適切な業務配置を行います。
免許取得支援の実施
整備工場業務に必要な免許取得に向けた支援制度を導入し、準中型・中型免許取得を促進することも有効です。
定期的な教育と指導
従業員に免許制度の正しい理解を促すために、定期的な研修や講習を実施します。特に新入社員や若手社員には、業務開始前に明確な免許範囲と運転可能な車両の説明を徹底することが重要です。
現在の免許制度では、普通免許の取得時期により運転できるトラックの範囲が大きく異なります。経営者世代が持つ免許範囲と現在の若手従業員が取得する免許範囲は著しく異なりますので、免許の種類と取得年月を明確に管理することが必須です。
自動車整備工場経営者として、免許制度を正確に理解し、社内での適切な運用と教育を行うことで、法令遵守だけでなく、事故やトラブル防止に役立てることができます。